EV軽自動車、実は “電気代” で差がつく?:都市部ユーザーに最適な「まちエネ」の活用法
近年、ガソリン価格の高騰や環境意識の高まりを受けて、軽自動車のEV(電気自動車)モデルが注目を集めています。日産サクラや三菱 eKクロスEV など、通勤や近距離の買い物にちょうど良いサイズと性能を備えたモデルが増え、初期費用さえ乗り越えられれば “燃料代ゼロ” の生活も夢ではありません。
しかし、そこで浮かび上がるのが「電気代ってどれくらいかかるの?」という疑問。
とくに都市部のマンションや戸建てに住んでいて、家庭用電源でEVを充電する場合、契約している電力プランによって電気代に大きな差が出ることをご存じでしょうか?
そこで注目したいのが、「まちエネ」の毎晩快適充電プラン。このプラン、ただの深夜割引ではなく、「EVユーザー向けに無料で充電できる枠が用意されている」というのが最大の特徴です。
この記事では、自身が関東地方で軽EVを所有し、「まちエネ」のこのプランに実際に契約して感じたことをベースに、具体的な電気料金の試算や無料枠を活用した節約術をわかりやすく紹介していきます。
まちエネってどんな電力会社?:EVユーザーに強い理由

「まちエネ」という名前は聞いたことがあるけれど、どんな会社が運営しているのか、どんな特徴があるのかご存じない方も多いかもしれません。
三菱商事とローソンの合弁会社が運営
まちエネは、三菱商事とローソンが共同出資して設立したMCリテールエナジー株式会社が運営する電力サービスブランドです。元々はローソン店舗の電力供給を目的に始まりましたが、現在は家庭向けにも広く展開されています。
企業色が強い印象を持たれがちですが、個人向けのプランにEVユーザー専用のメニューを設けている点は非常に特徴的です。
EV・PHEVユーザー向けの「毎晩快適充電プラン」
今回焦点を当てる「毎晩快適充電プラン」は、その名のとおり夜間(午前1時〜5時)に充電するEVユーザーに最適化された電力プランです。東京都を含む東京電力エリアでは以下のような条件で提供されています:
- 毎月、総使用量の20%までが無料充電枠として適用される
- 無料充電の対象は、午前1時〜午前5時の間の使用分
- EVまたはPHEVの保有が条件(車検証などの提出が必要)
- 自宅にEV充電設備が設置されていること
つまり、このプランは “夜間にしっかり充電する家庭” でこそ真価を発揮します。特に、私のように軽EVを日常使いしているユーザーにとっては、かなり実用的かつお得な仕組みと言えるでしょう。
毎月◯kWhまで無料!:軽EVユーザーが得する「無料充電電力量」の仕組み

「毎晩快適充電プラン」の最大の魅力は、毎月の電気使用量の最大20%まで無料でEVに充電できるという制度です。これは、EVやPHEVを保有している世帯で、深夜時間帯(午前1時〜午前5時)に電気を使った分が、使用量の20%まで無料で相殺されるという仕組みです。
では、実際にこの “無料枠” はどれくらい役立つのでしょうか?ここでは、EV軽自動車を例にシミュレーションしてみます。
三菱自動車 eKクロスEV でシミュレーション
例えば、筆者が実際に使用している eKクロスEV の場合、バッテリー容量は20kWh、満充電で実走行150km前後とされています。
月500 km走行した場合の消費電力量(軽EVの例)
私が使用している eKクロスEV などの軽EVでは、実走行時のエネルギー効率はおおむね約7〜8 km/kWh(=約125〜140Wh/km)とされています。
電気使用量の一例(家庭+EV充電)
- 家庭の電力消費:月180 kWh
- EV充電:月65 kWh
- 合計:245kWh
「家庭の電力消費:月180 kWh」とは、2人暮らしの家庭でエアコンや冷蔵庫、洗濯機などを標準的に使用している場合の平均的な使用量を想定したものです。
この場合、245 kWhの20% = 49 kWhまでは無料充電枠の対象となる可能性があり、月のEV充電の7〜8割を無料でまかなえることになります。
実質的な電費は “ほぼゼロ” も狙える
東京電力エリアの通常料金は、月120 kWhまでが29.80円/kWhです。これが50kWh以上無料になると、単純計算でも月1,500円相当以上の割引になります。
EVの「電費」が走行 1 kmあたり2〜3円以下という状況が、制度的に支えられているのは非常に強力です。とくに短距離メインのユーザーにとって、これはガソリン代と比較しても圧倒的なコストパフォーマンスです。
参考までに、軽自動車(ガソリン車)の走行コストは、実燃費20 km/L・ガソリン180円/Lで換算すると、走行 1 kmあたり約9円。EVならその3分の1以下で走れる計算になります。
実際いくら?:東京電力エリアのまちエネ料金でEVを充電した場合のコスト試算(40A契約編)
-visual-selection.png)
EVの自宅充電を最も効率よく行うには、契約アンペア(A)選びも重要です。今回は私が契約している40A(基本料金:1,800円/月)をベースに、東京電力エリアでの実質的な電気料金をシミュレーションします。
まちエネ(東京電力エリア)の基本料金と従量料金(2025年8月時点)
- 基本料金(40A):1,800円(税込)/月
- 電力量料金
- ~120kWh:29.80円/kWh
- 120~300kWh:36.40円/kWh
- 300kWh~:40.49円/kWh
試算:軽EV充電 65 kWh+家庭使用 180 kWh(合計245 kWh)
無料充電分(20%枠)を活用した場合の課金対象量
- 総使用量:245 kWh
- 無料充電枠:20% = 49 kWh
- 課金対象:245 – 49 = 196 kWh
電力量料金(概算)
- 120kWh × 29.80円 = 3,576円
- 76kWh × 36.40円 = 2,766円
- 合計:約6,342円
合計料金(月額)
- 基本料金(40A):1,800円
- 電力量料金:6,342円
- 合計:約8,142円(税込)
EV充電にかかる電費だけ見ると?
仮に65 kWhのうち49 kWhが無料で、課金対象は16 kWh程度とすると、
- 16kWh × 約30〜36円 = 480〜576円程度
月500km走って電費がワンコイン程度に抑えられる可能性があります。
ガソリン車と比べて7〜8割の燃料コスト削減が見込める点は、特に都市部・短距離利用の軽EVユーザーにとって非常に大きなメリットです。
ガソリン車と比較すると?
- 実燃費:20 km/L
- ガソリン価格:180円/L
- 必要量:500 km ÷ 20 km/L = 25 L
- 費用:25 L × 180円 = 4,500円
→ 同じ500km走っても、ガソリン車は約4,500円。EVなら約500円。
→ 約90%の燃料コスト削減が期待できるのは、特に都市部・短距離利用の軽EVユーザーにとって非常に大きなメリットです。
節約を最大化するためのテクニック:充電タイマーとスマートプラグの活用

「毎晩快適充電プラン」の恩恵を最大限活かすには、午前1時〜午前5時の “無料充電枠” 時間帯に正確に充電を行うことが鍵となります。
特に家庭用コンセントでEV充電を行っている場合、タイマー設定ができるかどうかが、月々の電気代を左右します。
EV本体の「充電タイマー機能」を活用する
近年の軽EV(例:三菱 eKクロスEV・日産サクラなど)には、標準で「タイマー充電機能」が搭載されています。これにより、毎晩1時から自動で充電が始まり、5時で止まるような設定が可能です。
設定方法は車種によって異なりますが、専用アプリやナビ画面から簡単に操作できます。
スマートプラグ+充電器で制御する方法も
もし使用中の充電設備がタイマー非対応であっても、スマートプラグやコンセントタイマーを活用すれば、手頃な費用で充電時間をコントロールできます。
例:1,500円〜3,000円程度の製品で以下のことが可能
- 夜間1時〜5時のみ通電
- スマホアプリでスケジュール設定
- 無線LAN経由でリモート操作
ただし、200 Vタイプの普通充電器には非対応の場合があるため、機器の仕様には注意が必要です。
200 Vタイプと100 Vタイプの普通充電器の違い
| 項目 | 200 Vタイプ | 100 Vタイプ |
|---|---|---|
| 電圧 | 200ボルト(専用回路必要) | 100ボルト(家庭用コンセント) |
| 充電時間 | 速い(軽EV満充電に約4〜6時間) | 遅い(軽EV満充電に約12〜14時間) |
| 設置 | 専用コンセント or 充電器の設置が必要 | 工事不要(差し込み式) |
| 対応機器 | 安全面からスマートプラグ非対応が多い | タイマー付き延長コードやスマートプラグでも制御しやすい |
| おすすめ | 急ぎ充電が多い人、昼夜問わず充電する人 | 短距離ユーザー、設置費を抑えたい人 |
200 Vタイプの普通充電器は、軽EVを数時間で充電できるため非常に便利ですが、専用回路の工事が必要で、スマートプラグなどによるタイマー制御が難しい場合があります。一方、100 Vタイプ(家庭用コンセント)での充電は時間はかかるものの、延長コードやタイマー機器との相性が良く、夜間充電との相性も抜群です。
「過充電」や「未充電」を避けるためのコツ
- タイマー設定を曜日ごとに調整して、週末だけ多めに充電する
- 実際の充電量と無料枠の上限(20%)を見ながら週1回だけ長めに充電する
こうした細かなチューニングによって、実質的な充電コストはゼロに近づけることが可能です。
契約前にチェック!:まちエネ「毎晩快適充電プラン」の注意点と落とし穴

まちエネの「毎晩快適充電プラン」は、EVユーザーにとって非常に魅力的な内容ですが、契約・運用にあたっていくつか重要な注意点があります。ここでは、私自身の体験や公式資料をもとに、見落としがちなポイントをまとめます。
EVまたはPHEVの保有が必須
このプランは「EVまたはPHEVを保有している方限定」です。契約時には車検証の写しなどの提出を求められる場合があり、条件を満たさないと契約が解除される可能性もあります。
自宅にEV充電設備があること
同一の需要場所(=契約住所)に電動車用充電設備が設置されていることが必要です。外出先や職場での充電がメインという場合、このプランのメリットを十分に享受できない可能性があります。
契約電流が30 A以上であること(40A推奨)
契約電流が30アンペア未満の場合は新規契約不可です(※2024年9月24日以前の既存契約者は除く)。EVの充電を自宅で行う場合、最低30 A、理想は40 A以上を確保するのが望ましいです。
日中の電気使用が多い家庭には不向きな場合も
このプランはあくまで「夜間充電」が前提です。日中の電力単価は通常プランと同等かそれ以上なので、昼間にエアコンやIHを多用する家庭は、かえって割高になることも。
電力量によっては無料枠が活用しきれないことも
たとえば、家庭の電力使用量が非常に少なく、月間総使用量が200 kWh以下の場合、無料枠(=使用量の20%)は40 kWh以下になります。EV充電を多く行う人にとっては「無料枠が足りない」と感じる可能性も。
このような条件を把握した上で、「自分のライフスタイルに合っているか?」を見極めることが、このプランを最大限活用するカギになります。
まとめ:都市部の軽EVユーザーにこそすすめたい「まちエネ」活用術

軽自動車EVを効率よく運用したいなら、電気契約の見直しこそが最大の節約ポイントです。特に都市部在住で、
- 通勤・買い物中心で走行距離が月500 km程度
- 自宅に充電設備があり、夜間に充電できる
- 家庭の電気使用量もそれなりにある(200〜300 kWh/月)
という条件に当てはまる人には、「まちエネ」の毎晩快適充電プランは現時点で最もコストパフォーマンスが高い選択肢のひとつと言えるでしょう。
都市部ユーザーは「短距離移動が中心」「昼間不在が多い」「自宅充電が前提」などの条件が揃いやすく、まちエネのような夜間電力が有利なプランとの相性が非常に良いのが特徴です。
正直に言えば、「EVって結局、電気代どうなの?」という不安はありました。しかし、実際にプランを切り替えてみた今は、ガソリン代が消えた実感と、家計への安心感があります。
特に「無料充電枠」の存在は大きく、実質的に “タダで移動できている” 感覚があるのは、想像以上に気持ちがいいものです。
今後、再生可能エネルギー比率の拡大やEV普及によって、このようなプランはさらに増えていくと予想されます。一方で、終了や改定のリスクもあるため、契約条件のチェックや更新タイミングの管理は継続して行っていく必要があります。
EVライフは「車選び」で終わりではなく、「電気契約」まで含めて最適化することで、本当の意味での “コストメリット” が見えてくると実感しました。EV検討中の方やすでに所有している方も、一度ご自身の契約プランを見直してみてはいかがでしょうか。
おことわり
本記事の内容は、筆者の個人的な体験と2025年8月時点で公開されている資料(「まちエネ」毎晩快適充電プランの電気需給約款・重要事項説明書など)をもとに作成しています。
料金体系や契約条件は今後変更される可能性がありますので、最新の情報は必ず公式サイト(https://www.machi-ene.jp/)をご確認ください。
また、電気料金や充電コストに関する試算は一般的な条件を用いた参考値であり、すべての利用者に同様の効果があることを保証するものではありません。実際の料金や効果は、ご家庭の契約内容や使用状況によって異なります。
本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。
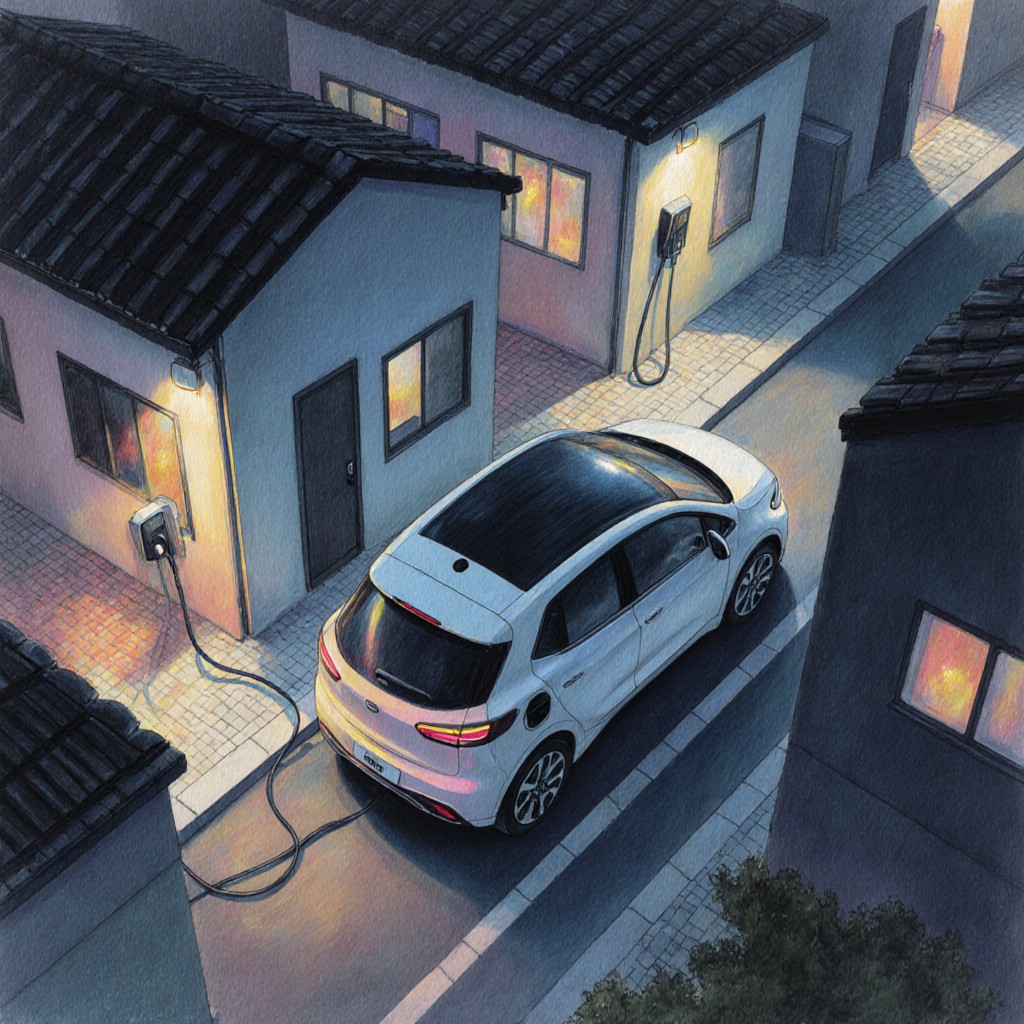








コメント