最近よく見かける「プラントベース」って何?
スーパーやコンビニ、外食メニューでも目にするようになったこの言葉。けれど、「ベジタリアンやヴィーガンの人のものでは?」と距離を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は今、プラントベース食品(PBF)は特定の層だけでなく、ふだんの暮らしの “ちょっとした選択肢” として急速に広まりつつあります。その背景には、健康志向や環境配慮、技術革新といった社会全体の大きな動きがあります。
この記事では、そんなプラントベース食品の基本の定義から、国内外の市場規模、成長理由、そして私たちの暮らしへの取り入れ方までを、データと事例を交えて丁寧に解説します。
“なんとなく気になるけど、まだよく知らない”
そんなあなたにこそ届けたい、プラントベースのいま。そしてこれからです。
プラントベースとは?:基本の定義と背景

「プラントベース(Plant-Based)」とは、動物性原料を一切または大幅に除いた食品や生活用品を指す言葉です。似た概念に「ヴィーガン」がありますが、以下のような違いがあります。
この柔軟性こそが、近年の広がりのカギになっています。いわば “ヴィーガンよりも気軽に取り入れやすい入り口” として、日常に浸透し始めているのです。
日本における背景と親和性
日本はもともと、豆腐・味噌・納豆といった大豆製品を中心とした伝統的な植物性食文化が根づいています。そこに欧米発のソイミートやプラントミルクなどの代替技術が加わることで、独自の広がりを見せています。
さらに、国内調査では約79%の消費者が「健康目的で野菜摂取を意識している」というデータもあり(SME Japan調べ)、PBFのニーズと土壌が整っていることがうかがえます。
世界/日本の市場動向
世界的には、2025年に約1,422億ドル(約17兆円)、2035年に約4,418億ドル規模の市場に成長する見込みで、特にミート代替製品が主導しています(CAGR:約12%)。
日本では、2021年の植物性食品市場が約340億円に対し、2025年には約730億円まで倍増すると予測されています(CAGR:約18%前後)。
ヴィーガン食品市場(ミート・乳製品代替等)は2024年に約12億米ドル(約1,600億円)となり、2033年には27億ドル(約3,800億円)に達する見通しです(CAGR:約9.7%)。
CAGRとは?
CAGR(Compound Annual Growth Rate:年平均成長率)は、ある一定期間における投資や売上などの年平均の成長率を示す指標です。日本語では「年率換算成長率」や「複利年成長率」とも訳されます。
初年度と最終年度の数値だけを使って計算し、その期間中に毎年一定の割合で成長したと仮定したときの年平均成長率を表します。
実際の年ごとの変動は無視されるため、成長トレンドをシンプルに把握したいときに便利です。
「なぜ今」注目されているのか?
- 健康志向:
- 食習慣の多様化・腸活志向増加。高血圧・動脈硬化など生活習慣病予防ニーズ。
- 環境配慮:
- 「食から地球を守る」意識の高まり。
- 食肉生産が温室効果ガス・森林破壊の一因であるという世界的認識。
- テクノロジーと企業の取り組み:
- 国内外の企業が、味・食感・価格の向上に力を入れ、日常食品としての質が底上げ。
出典:The Rise of Plant Based Businesses in Japan’s Food Industry
Foodtech Sector in Japan
Plant-Based Food Market
Japan Vegan Food Market Expected to Reach USD 2.7 Billion by 2033 – IMARC Group
Vegetarian Snacks Market Landscape 2025: Regional and Global Insights
市場規模と成長数字
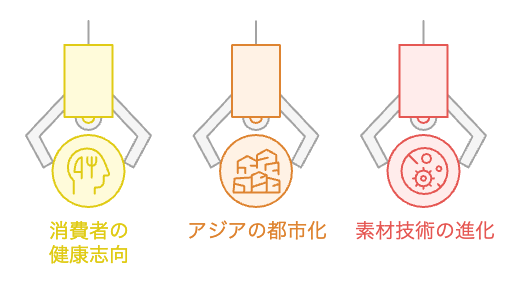
プラントベース食品は今や「流行」ではなく、構造的な成長市場となっています。日本・世界それぞれの動向を見てみましょう。
日本市場の動向
- 2021年:約340億円 → 2025年:約730億円(予測)
- この約2.1倍の成長は、CAGR(年平均成長率)で約18%に相当します。
- ミート代替市場のみで2024年:約1,600億円 → 2033年:約3,800億円(CAGR:約9.7%)
- 豆類たんぱく食品市場(2021年時点):約452億円
特に注目すべきは「大豆ミート」や「豆乳ヨーグルト」など、生活の中で違和感なく使える食品の成長です。
世界市場との比較
- 2025年:約1,422億ドル(約17兆円) → 2035年:約4,418億ドル(約44兆円)
- こちらもCAGRは約12%と高水準で推移。主に北米・ヨーロッパ・アジア太平洋地域での成長がけん引しています。
特にアジア圏では、都市部の食習慣変化とサステナ意識の高まりが成長を支えており、日本もこの流れに乗っている形です。
チャネルの多様化が加速
PBF商品は以下のような販路で広がりつつあります:
- スーパー・ドラッグストア:
- 常温保存できるソイミートやプラントミルク
- コンビニ:
- アイスやスイーツ、惣菜パンなど「日常使い商品」
- 外食/テイクアウト:
- ファストフード、フェス系キッチンカー
- EC(Electronic Commerce:エレクトロニック・コマース、日本語では「電子商取引」):
- 専門ブランドによる冷凍・セット食品など
これらの流通拡大が「知ってるけど、買ったことない」層の行動変容を後押ししています。
数値サマリー表
これらの市場動向をわかりやすくまとめると、次のような数値で整理できます。
| 指標 | 数値 | 出所 |
|---|---|---|
| 国内市場規模(2021‑25年) | 340億円 → 730億円予測 (CAGR 約18%) | SME Japan (ウィキペディア, Grand View Research) |
| ミート代替市場規模(2024‑33年) | USD 980M → USD 5,448M予測(CAGR 21%) | IMARC Group (IMARC Group, YouTube) |
| ヴィーガン食品市場(2024‑33年) | USD 1.2B → USD 2.7B予測(CAGR 約9.7%) | IMARC Group (giiresearch.com, IMARC Group) |
| グローバルPBF市場(2025‑35年) | USD 1,422B → USD 4,418B(CAGR 約12%) | FMI (Future Market Insights, IMARC Group) |
| 途上アジア地域の成長率 | CAGR 約10‑12% | FMI (Future Market Insights, innovamarketinsights.com) |
※USD → 円は年平均レート(1USD=150円前後)で換算。
成長の裏にある市場変化とは?
- 消費者の “気軽な健康志向”:
- ヴィーガンではなくても「たまに使う」柔軟な選択層(フレキシタリアン)や、ダイエットや腸活などの健康目的層が増加。
- アジアの都市化・意識変化:
- 日本も含め、都市圏中心にPBF導入が進み、購買動線と商品可視化が加速。
- 素材技術の進化:
- 食感や味わいの改善、価格低下が進み、価格対品質の両立が実現。
出典:The Rise of Plant Based Businesses in Japan’s Food Industry
なぜ急成長?:3つの背景視点

日本のプラントベース食品(PBF)がここまで急成長した背景には、大きく以下の3つの要因があります。
1. 健康志向の高まりとライフスタイルの変化
- 日本では 約79% の人が健康目的で野菜摂取を意識しており、PBFはその代替手段として受け止められています。
- 特に「腸活」「たんぱく質の植物性補給」などのトレンドが強まり、「プラントベースミート」「豆乳ヨーグルト」「プロテインバー」といった商品が人気です。
「プラントベースプロテイン」「プラントベースプロテインバー」の検索数が増加しており、この需要を裏付けています。 - 生活習慣病対策や減塩・低脂肪ダイエットの観点から、動物性たんぱく質の代替としての役割が注目され、主婦層や中高年にも着実に支持されています。
2. 広がる環境意識とサステナブルな暮らしへの関心
- 畜産業は温室効果ガスの約14.5%を占め、大量の水資源・飼料・土地が必要です。この背景が欧米メディアや日本の教育にも取り上げられ、消費者の意識変化が進んでいます。
- プラントベース食は「小さな選択で環境にやさしい暮らし」が体現できる手段として、Z世代から中高年世代まで広い世代に受け入れられています。
- 企業側でも脱炭素を掲げる動きが増えており、食品メーカー・飲食店が「環境アピール」を強化、その一環としてPBFへの需要を捉えています。
3. テクノロジーの進化と企業の積極的な参入
- 世界では「インポッシブル・フーズ」や「ビヨンド・ミート」といった企業が先行しており、日本でも大豆ミート・豆乳・エンドウ豆たんぱくなどを原料にした技術開発が進んでいます。
味や食感の改良も日々進化しています。 - 国内でもR&D(研究開発)の取り組みが強化されており、「ソイチーズでとろけるピザ」や「プラントベースうなぎ」など、これまでにないユニークな商品が続々と登場しています。
たとえば、「プラントベースソフトクリーム」や「プラントベースうなぎ」などの検索数が720〜1,000件ほどあり、季節限定商品としての注目度が高まっています。 - さらに、コンビニやファストフードなどの既存の販売チャネルにもプラントベース食品(PBF)が取り入れられ、「特別な食事」ではなく「身近な選択肢」として定着しつつあります。
背景まとめ:健康・環境・技術が3軸で重なる
この3つの要因が以下のように重なることで、爆発的な市場拡大につながっています:
これらが消費者・企業・社会のトレンドと構造的に一致していることこそ、2025年にかけてPBFが加速度的に浸透した理由です。
出典:Livestock’s Long Shadow
Environmental vegetarianism
暮らしとの接点・商品紹介

市場が急成長する一方で、プラントベース食品(PBF)は私たちの暮らしにすでに根づきつつあるのを実感する場面が増えています。最近の注目商品を挙げながら、日常への浸透度を見てみましょう。
スーパー/コンビニで買えるPBF
ファミリーマート「植物生まれのクリームサンド(クッキー&クリーム)」他
ファミリーマートは2025年6月、「植物生まれのクリームサンド(クッキー&クリーム)」などの植物性由来スイーツシリーズを展開しています。植物性原料だけでクリーム感・食感を再現した商品です。
「スナックにも気をつけたい」という人にも手が出しやすく、日常的なおやつ選びとして自然に選べる一品です。
出典:シリーズ初のワンハンドデザートが新登場! おいしい植物性由来「ブルーグリーンプロジェクト」第6弾 前回大好評の「シャインマスカットグミ」など全5種類を発売
eclipseco(エクリプスコ)プラントベースアイス
2025年4月より、都内ファミマ約2,400店で展開中。乳・卵を使わずに濃厚でクリーミーな口当たりを実現し、トランス脂肪酸・コレステロール「ほぼゼロ」でヘルシーな点も訴求されています。
出典:濃厚でクリーミーな100%植物性アイス「eclipseco(エクリプスコ)」都内ファミリーマートで新商品を発売!
外食/テイクアウトでの進化
キッチンカー・イベントでのPBFソフトクリーム
2025年春、大阪・関西万博の外食パビリオンでは乳・卵不使用のプラントベースソフトクリームが提供されました。老若男女をつなぐ“コミュニケーションツール”として、世代を問わず好評との報道も。
出典:大阪・関西万博開幕:ORA外食パビリオン=日世 ソフトクリームの進化を体現
ザ グレート バーガー(原宿・渋谷)の100%PBFバーガー
渋谷・原宿にある「ザ グレート バーガー」では、大豆由来代替ミート&卵不使用のバンズで仕上げた “完全プラントベースバーガー” を提供中。高価格帯ながら、味や食感で高評価を得ています。
出典:原宿&渋谷のバーガーショップ・ザ グレート バーガーに新メニュー「100%プラントベースバーガー」
家庭楽しみも広がるPBF食品
日清「プラントベースうなぎ 謎うなぎ」
2025年7月3日からオンライン限定で7000セット発売された、「うなぎ風」プラントベース食品で、昨年は1分で5000セットが完売した人気商品です日本食糧新聞・電子版+11日清食品グループ+11Food Diversity.today+11。
- 3層構造と金型・炙り加工で本物の蒲焼に迫るリアル再現。
- 健康・環境・技術性の高い訴求力があり、実食レポでも「プラントベースを忘れる味」と評されています。
- アクセスが難しいオンライン限定ながら、それでも社会的反響や注目度の高さがうかがえます。
出典:「プラントベースうなぎ 謎うなぎ」
日清食品「謎うなぎ」プラントベースで驚きのふっくら食感 名店監修のもと風味・脂感もアップ
日清食品が「プラントベースうなぎ 謎うなぎ」を2025年7月3日に数量限定発売
暮らしにどう取り込む?3つのストーリー
| シーン | 商品例 | 提案ポイント |
|---|---|---|
| 自宅おやつ・子ども向け | クリームサンド、アイス | おいしさ重視でもヘルシーな選択肢に |
| 週末イベント体験 | ソフトクリーム、謎うなぎ | 特別感のある新鮮な体験で関心を惹ける |
| 日常の食卓・テーブル彩り | グリッシーニ、代替卵 | 既存食材と混ぜやすく、無理なく導入可能 |
未来展望と生活導入ヒント

市場と技術が進化する中で、プラントベース食品(PBF)は今後どのように進化していくのか。そして読者が日常に取り入れるヒントを提案します。
2030年に向けて加速する市場の広がり
日本のプラントベース食品市場は、2024年時点で約2,300億円(23億ドル)の規模ですが、2033年には約4,800億円(48億ドル)まで拡大すると予測されています。年平均成長率(CAGR)は約9.7%と見込まれており、安定した成長が期待されています。
また、大豆などを使って肉のような食感を再現する「テキスチャード・ベジタブル・プロテイン(TVP)」の市場も伸びており、2025年には約46億円(4,620万ドル)に達すると予想されています。これにより、加工技術の進化がさらに加速すると考えられています。
食と農をつなぐ新たな可能性
プラントベース食品の原料として使われる大豆やエンドウ豆などを日本国内で栽培する取り組みが進めば、食料の自給率を高めるだけでなく、地域の農業にも良い影響を与えると期待されています。
政府も環境に配慮した農業政策を進めており、プラントベース食品と地域農業が共に発展する未来が見えてきています。
環境政策と連動する成長のチャンス
日本政府は、2035年までに温室効果ガスを60%削減し、2040年までに再生可能エネルギーの比率を50%に引き上げるという目標を掲げています。
こうした環境政策と、プラントベース食品の普及がうまく連動することで、持続可能な「脱炭素社会」を支える新しい食のインフラとして、プラントベース食品はますます重要な役割を担っていくでしょう。
生活に取り入れるためのヒント
- フレキシタリアンを意識した「小さな置き換え」から:
- いきなり完全PBFにせず、週に1〜2日「プラントベースミールデー」を設けるスタイルが無理なく続きます。納豆や豆腐がある和食にプラスするように、代替肉入りカレーやハンバーガーを試すのが◎。
- 家庭菜園や発酵含む “自家製ルーティン” との組み合わせ:
- 例:自宅で育てたハーブ入り豆乳ヨーグルト・味噌を使ったサラダドレッシング。
CSA(地域支援農業)利用者のうち、「環境教育」や「社会貢献」を重視する人は多く、PBFと相性が良いという調査結果もあります。
- 例:自宅で育てたハーブ入り豆乳ヨーグルト・味噌を使ったサラダドレッシング。
- 便利な既製品で「賢く活用」:
- スーパーやコンビニで気軽に試せる「クリームサンド」や「プラントベースアイス」を、まずはおやつに取り入れてみるのがおすすめ。
味を確かめつつ、自分なりの「今日のご褒美」として生活に溶け込ませられます。
- スーパーやコンビニで気軽に試せる「クリームサンド」や「プラントベースアイス」を、まずはおやつに取り入れてみるのがおすすめ。
- 家族参加型の体験ルーティンを楽しむ:
- 休日にキッチンカーや専門店を巡って、新作PBFスイーツや「プラントベースうなぎ」を親子で楽しむ体験も◎。
楽しさと健康両立を意識するライフスタイルを共感的に届けられます。
- 休日にキッチンカーや専門店を巡って、新作PBFスイーツや「プラントベースうなぎ」を親子で楽しむ体験も◎。
まとめ:未来の“当たり前” を、今日からひとつ

ここまで見てきたように、プラントベース食品(PBF)は「一部の人のもの」から「暮らしの中の選択肢の一つ」へと大きくシフトしています。2025年、日本市場の規模は730億円に迫り、世界的にも食の在り方を再構築するうねりが生まれています。
この背景には、健康への関心、地球環境への思いやり、そして企業や技術の進化があります。特に日本はもともと豆腐や納豆などの植物性食材に親しんできた文化的下地があり、PBFとの親和性は非常に高いと言えます。
ただ、すべてを置き換える必要はありません。「週1回のお試し」「おやつだけ代替」「イベントで体験」など、今の暮らしに負担をかけない “ゆるい取り入れ方” こそが、これからの主流になるでしょう。
Gradatim Labでは、これからもこうした暮らしに根ざした変化を、丁寧に、積み重ねるように取り上げていきます。まずは一度、身近なプラントベース商品を手にとってみませんか?
そこには、身体にも地球にも、やさしい選択の始まりがあるかもしれません。
おことわり
本記事は、一般公開されている統計資料・企業リリース・市場調査レポートなどに基づいて作成しています。数値は調査年や為替レートにより変動の可能性があるため、あくまで参考情報としてご覧ください。
また、掲載している商品情報・価格・販売状況などは2025年7月時点のものであり、今後変更される場合があります。ご購入やご利用の際は、各公式情報をご確認ください。
当メディアは特定企業・商品を推奨するものではなく、暮らしの視点から「選択肢のひとつ」としてプラントベース食品に関心を持つきっかけとなることを目的としています。
本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。









コメント