成果が出ない時間にこそ、育つものがある
ブログを始めたのに、アクセスが増えない。
収益も出ない。書いても反応がない。—— そんな停滞感に、焦りを感じていませんか?
多くのブロガーが「結果が出ない=意味がない」と思い込み、この時期に筆を止めてしまいます。けれど実は、その “成果が出ない時間” こそ、未来のあなたを育てる最も重要な時期なのです。
中国の思想家・荘子は、「無用の用(むようのよう)」という言葉を残しました。一見、役に立たないように見えるものこそ、実は最大の価値を持つ —— そんな逆説的な真理です。まっすぐに伸びた木はすぐに伐られるが、曲がった木は長く生き延びる。荘子はこの比喩で、“すぐ役立たないこと” の中にこそ本質があると説きました。
ブログ運営にも、この思想は驚くほど通じます。
PVや収益といった “表の数字” ばかりを追いかけると、短期的なテクニックに偏り、本質的な「書く力」や「読者を理解する力」が育ちません。逆に、誰にも読まれない時期に試行錯誤し、キーワードを検証し、構成を練る —— その過程こそが、後に強力な土台となって返ってきます。
この記事では、「無用の用」の思想をヒントに、ブログ運営を “焦らない・急がない・積み上げる” という観点から再定義します。
今はまだ結果が出ていないとしても、その時間を「未来を育てる投資期」として活かすための視点を、一緒に整理していきましょう。
「成果がない時間」こそ最高の学習期
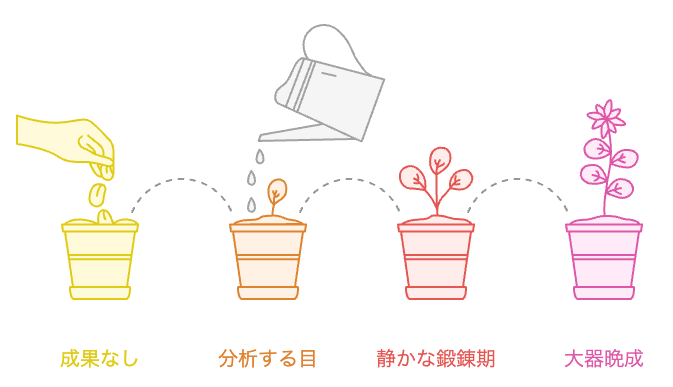
ブログを続けていると、どうしても「数字が動かない時期」が訪れます。
Google Search Consoleを開いても、クリック数は横ばい。記事を増やしてもPVは伸びず、「何をやっても効果がない」と感じる。そんな時期ほど、最も多くの人が離脱していきます。
しかし、ここで止めてしまうのは本当にもったいない。
なぜなら、成果が見えないこの時期こそ、学習と成長が最も濃密に起きている期間だからです。
このフェーズでは、あなたの中で「分析する目」が育っています。
どんなキーワードが検索されているか、タイトルにどんな言葉を置くとクリックされるか、読者がどの段落で離脱しているか。数字は小さいけれど、そこには確実に “読者の反応データ” が詰まっています。
この観察と仮説検証の繰り返しこそが、後に「書く力」と「構成力」を支える思考筋肉になります。
最初から完璧な構成やSEOライティングができる人などいません。
むしろ、検索意図を読み違えたり、構成がずれて反応が取れなかったりする失敗こそが、ライターとしての感覚を磨く教材です。
一見、無駄に思える記事リライトやキーワード試行も、全てが “データ蓄積” という形であなたの中に残っていきます。
たとえば、「CTRが低いタイトル」を修正して反応が変わったとき、あなたは “読者の心理” を一つ理解したことになります。
この積み重ねは誰にも奪われない無形資産です。
荘子の言葉に「大器晩成」という考えがあります。
大きな器ほど、形を成すまでに時間がかかる。
ブログ運営も同じで、見えない時期ほど深く根を張っているのです。
だからこそ、焦らずに “何を学べているのか” に意識を向ける。
結果ではなく、検証の過程そのものに価値を見出す。
それが、後に大きな成果へとつながる第一歩になります。
成果が出ない時期は、静かな鍛錬期です。
あなたが記事を積み重ね、仮説を立て、また検証する。
その一つひとつの試行錯誤が、後の「精度」と「説得力」を生み出していきます。
“数字が動かない時間”は、“思考が動いている時間” でもあるのです。
荘子の “曲がった木” に学ぶ、独自性の守り方

荘子の『山木篇(さんぼくへん)』にこんな話があります。
山に大きな木が生えている。まっすぐでもなく、節だらけで、材木にもならない “曲がった木”。
人々はその木を役立たずだと笑い、誰も伐ろうとしません。けれどその木は、だからこそ長く生き続け、やがて人々が木陰で休む場所になった —— という寓話です。
この “曲がった木” こそ、荘子が説いた「無用の用」の象徴です。
「すぐに役立たない」ものが、「長く存在する」ための理由を持っている。
そしてこの考え方は、今のブログ運営にもそのまま通じます。
ブログを続けていると、どうしても他のブロガーと比べてしまいます。
「同じ時期に始めたあの人はもう月1万PV」「あのサイトはすでに収益化」 —— そんな数字を見ると、焦りが生まれ、効率を追い求めたくなります。
けれど、他人のスピードや型に合わせて書くことは、自分の “木の形” を無理にまっすぐにしようとするようなもの。短期的には整って見えても、長期的には自分の根を弱めてしまいます。
荘子はこうした “まっすぐさ” を批判し、「曲がっていることの強さ」を説きました。
それは「他人と違っていい」「使われなくていい」という放棄ではなく、“自分らしさを損なわずに生きる戦略” です。
ブログで言えば、他人のテンプレートをなぞるのではなく、自分の思考・経験・価値観に根ざしたテーマや文体を磨いていくこと。
効率や即効性を求めすぎず、“自分の曲がり方” を意識的に守ることが、長く続くブログ運営の鍵になります。
アルゴリズムや流行の変化が激しい時代ほど、この姿勢が重要です。
検索上位を一時的に取っても、トレンドが変わればすぐに順位は入れ替わります。
しかし、“自分にしか書けないテーマ” や “体験から生まれる言葉” は、他者が模倣できません。
それは、誰にも伐られない「曲がった木」のような存在です。
たとえアクセスが少なくても、あなたの言葉に共感してくれる人は必ず現れます。
その少数の読者こそが、あなたのブログを支える最初の根っこになります。
他者と比べるより、自分の木がどんな形で成長しているのかを見つめる。
その“曲がり”が、やがてあなたの強みになるのです。
無用の用=レバレッジの下地
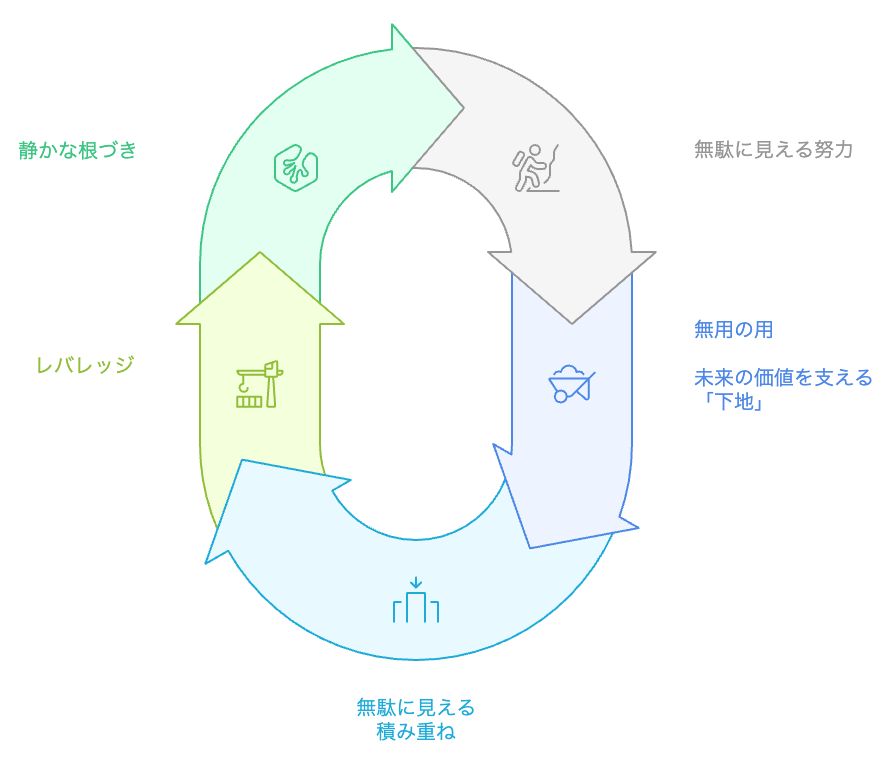
「これ、意味あるのかな?」
ブログを続けていると、そんな疑問が何度も頭をよぎります。
1日かけて書いた記事が読まれない。内部リンクを整理してもPVが動かない。
短期的に結果が見えない作業ほど、「無駄かもしれない」と感じやすいものです。
しかし、その “無駄に見える積み重ね” こそが、後に強力なレバレッジとして働きます。
荘子が説いた「無用の用」とは、まさにこのこと。
今は役立たないと思っている行動が、未来の価値を支える「下地」になっているのです。
たとえば、過去に書いた記事。
埋もれていたとしても、1年後に別の記事と内部リンクでつながった瞬間、検索流入の導線として蘇ります。
そのリンク構造が蓄積すれば、あなたのブログは「知識の森」のように機能し始め、1本1本の記事が “枝” としてお互いを支え合います。
この “構造の厚み” は、後から作ろうとしても簡単にはできません。
ナヴァル・ラヴィカントは「レバレッジ(Leverage)」を、「少ない労力で大きな成果を生む構造」と定義しました。
彼は成功の方程式をこう示しています。
方向 × 継続 × レバレッジ = 成果
方向を誤れば、いくら努力しても前に進めません。
しかし、正しい方向に少しずつ力を積み上げることで、時間があなたの味方になり、複利的な成果が生まれていきます。
この“方向” を見極める力こそ、成果が出ない時期に育まれるものです。
検索意図を考え、構成を練り、反応を分析する —— これらの思考が、あなたの「判断軸」を形づくります。
その軸が定まると、コンテンツの一貫性が生まれ、自然とレバレッジが効くようになります。
実際、長期的に成果を上げているブロガーほど、「すぐに成果が出ない施策」を淡々と続けています。
たとえば、記事テンプレートの改善、カテゴリ構造の見直し、読者ニーズの棚卸し。
これらは瞬間的なPVアップをもたらさない代わりに、後々「検索エンジンに評価される設計」や「読者が回遊しやすい導線」として機能し始めます。
短期思考では見落としがちな “無用の時間” を、未来のレバレッジへ変える。
そのためには、「積み上げる行動」を“投資”として捉える視点が欠かせません。
記事を書き、リライトし、内部リンクを張り、キーワードを検証する —— それらは単なる作業ではなく、すべてが“構造的資産”の構築です。
いまの努力がすぐに報われなくても、安心してください。
あなたが積み重ねているデータ、ノウハウ、記事構造、文章表現は、すべて未来のあなたを助ける「レバレッジの準備」です。
焦らず、方向を見失わずに、積み上げ続ける。
それが、無用の用を “成果を生む仕組み” へと変える最も確かな方法です。
読まれなくても続けられる仕組みを作る
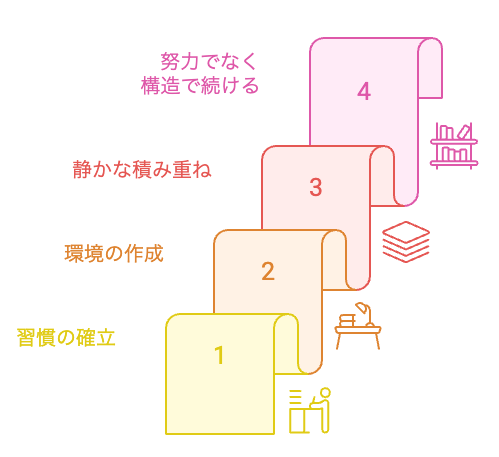
「続けることが一番難しい」 —— これは、すべてのブロガーが一度は口にする言葉です。
書いても読まれず、反応もなく、モチベーションが下がる。
そんなときに “根性” や “気合” に頼ると、燃え尽きてしまいます。
必要なのは、 読まれなくても続けられる “仕組み” を持つことです。
意志ではなく、環境と構造で続ける。
それが、長期的にブログを育てるための最も現実的な方法です。
たとえば、WordPressテーマの「SWELL」には、更新やリライトを効率化する設計が多くあります。
再利用ブロック、装飾のテンプレート化、目次の自動生成。
こうした“負担を減らす仕組み”は、モチベーションの波を平準化し、継続を助けます。
無理して毎日完璧な記事を書くのではなく、「10分で更新できるフォーマット」を作っておく。
それだけで、「継続の壁」は一段と低くなります。
また、“習慣化” も強力な仕組みです。
朝の15分で構成を練る、夜に1文だけ追記する、週末にGSCデータを眺める。
このように行動のハードルを下げると、「書けない日」ではなく「少しでも触れる日」が増えます。
やる気がなくても、手を動かせる “儀式” を自分の生活に埋め込む。
それが、ブログを生活の一部に変える第一歩です。
さらに、「分析の自動化」も有効です。
たとえば、スプレッドシートにGSCデータを自動連携し、クリック数やCTRを可視化する。
この仕組みを作ることで、感情に左右されずに「事実で振り返る」習慣ができます。
結果を追うのではなく、“観察すること” を目的化する。
このメンタル設計が、焦りを遠ざけ、冷静な改善サイクルを維持します。
そして何より、「稼がない勇気」を持つこと。
短期的な収益を優先すると、記事テーマが狭まり、モチベーションが数字に依存してしまいます。
一方、「今は土台を磨く時期」と割り切れば、収益化の圧力から自由になり、本質的な価値提供に集中できます。
結果的にその方が、後から安定した成果を生みやすくなるのです。
ブログ運営は、感情よりも構造です。
精神論ではなく、“やめづらい環境”を意図的に作る。
自分を責めず、仕組みで守る。
そうすることで、ブログは「努力するもの」から「自然に積み重なっていくもの」へと変わります。
“無用の用” の視点で言えば、読まれない時間もまた必要な養分です。
焦らず、仕組みの中で静かに積み上げる。
その過程が、未来のあなたを支える「信頼残高」を増やしていきます。
結語:無用の時間が、未来の “信頼残高” を積む

ブログを続けていると、「何のために書いているんだろう」と感じる瞬間があります。
数字が動かない日々、誰からも反応がない記事、報われない努力。
けれど、その “無用に思える時間” こそが、あなたの未来を静かに形づくっています。
記事を書くたびに、あなたは「言葉を選ぶ力」を磨いています。
リライトするたびに、「読者の気持ちを想像する力」を鍛えています。
そして試行錯誤を記録に残すたびに、あなた自身の「信頼残高」が少しずつ積み上がっていくのです。
荘子が説いた「無用の用」は、単なる哲学ではありません。
それは、“すぐに役立たないもの” を見捨てずに抱え続ける勇気のこと。
短期の成果を手放し、長期の価値を信じる姿勢そのものです。
あなたが書き続けた日々は、たとえ今は報われなくても、確実に誰かの役に立つ日が来ます。
たとえば、数年前に書いた記事が、ふと誰かの検索結果に現れ、その人の行動や考え方を変えるかもしれません。
それは「その瞬間のためだけに存在する文章」ではなく、「時を超えて残る信頼の証」です。
この “残り続ける力” こそ、ブログというメディアの最大の魅力です。
リベ大でもよく語られる「信頼残高」という言葉。
お金よりも、評価よりも、あなたの積み上げた行動そのものが、最終的に大きな価値を生みます。
読まれない時期の努力も、学びのメモも、すべてがその残高を増やしています。
だからこそ、焦らずに歩き続けてください。
無用に思える時間を恐れず、そこに意味を見出す。
その静かな積み重ねが、未来の “読者からの信頼”や“安定した成果” へとつながっていきます。
書くこと自体が、報酬になる。
それが、「無用の用」で生きるブロガーの在り方です。
おことわり
本記事は、筆者自身のブログ運営経験および学びをもとにした考察・記録です。
記載されている内容は特定の結果や収益を保証するものではなく、各自の状況や目的に応じてご判断ください。
引用した哲学的概念(荘子の思想・ナヴァル氏の言葉等)は、文脈をわかりやすくするための一般的な解釈を含みます。
運営環境(テーマ・分析ツール・SEO仕様)は執筆時点の情報であり、今後変更される場合があります。
本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。







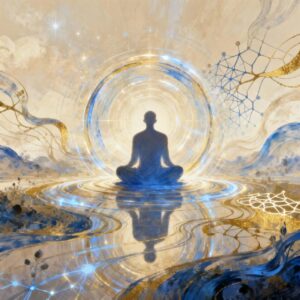

コメント