「健康のために始めたこと」が続かない理由とは?
40代になってから、「なんとなく不調」が増えたと感じていませんか?
私もそうでした。疲れが抜けにくくなったり、以前と同じ生活では体型が崩れたり…。それをきっかけに「健康のためにいい」とされることを少しずつ取り入れてきました。
青汁、サプリ、糖質制限、運動習慣、早寝早起き。健康に関する情報はあふれていて、「とにかく何かやらなきゃ」という気持ちになりがちですよね。
でも実際は ――「頑張って取り入れたはずなのに、続かない」「むしろ疲れてしまった」ということも、少なくありませんでした。
その経験を通して私が気づいたのは、「健康習慣は、やることを増やすだけが正解ではない」ということ。
むしろ、自分に合わなかった習慣を “やめる” ことで、体も気持ちもずっとラクになることもあるのです。
この記事では、私が40代で見直した「健康のためにやめたこと」を5つご紹介します。
無理なく、長く続けられる健康習慣を見つけたい方のヒントになればうれしいです。
① ストイックな糖質制限をやめた:疲れやすく、気分も不安定に

30代後半から「なんとなく太りやすくなった」と感じていた私は、巷で話題だった「糖質制限ダイエット」に飛びつきました。
白米やパンを控え、食事は基本的に「たんぱく質と野菜」が中心。最初の1〜2週間は体重もスッと落ちて、満足感がありました。
ところが1ヶ月を過ぎた頃から、以下のような変化が起きました。
- 昼過ぎになると頭がぼーっとする
- イライラしやすくなった
- 階段を上ると軽い動悸を感じる
- 便秘気味になった
明らかに「体調が良くなるどころか不安定になっている」感覚があったんです。
科学的にも「極端な糖質制限」はリスクあり
糖質は脳の主要なエネルギー源であり、完全にカットしてしまうと注意力・記憶力・気分の安定性が低下するという研究があります。
また、腸内環境のバランスにも影響が出る可能性があり、プレバイオティクス(糖質の一部)は善玉菌のエサとして必要とされています。
やめてからどう変わったか?
私は思い切って、当時朝食に白米を “軽く一膳” だけ復活させました。これだけで以下のような変化がありました。
- 朝の集中力が上がった
- イライラが減った
- 便通が安定した
また、糖質の質にも意識を向けるようになり、「発酵性食物繊維が摂れるもの」を積極的に選ぶようにしました。
代替提案:糖質を敵にしない“腸活習慣”でサポート
「糖質=悪」と決めつけるのではなく、腸内環境を整える食習慣をベースにした方が、私にとっては健康的でした。
今では、朝に乳酸菌入り青汁を取り入れるのが定着しています。以下の記事は、糖質の摂取と腸内環境のバランスを意識したい方にもおすすめです。



出典:Effect of low-carbohydrate diet on depression and anxiety: A systematic review and meta-analysis of controlled trials
Efficacy of low carbohydrate and ketogenic diets in treating mood and anxiety disorders: systematic review and implications for clinical practice
Sugar and the Brain
Low-carbohydrate weight-loss diets. Effects on cognition and mood
Low-carb diets can affect dieters’ cognition skills
② 就寝前のスマホ完全禁止をやめた:「ルール疲れ」が逆に眠りを妨げた

「寝る前はスマホを見ない方がいい」
これは多くの情報で語られていて、私も一時期、22時以降はスマホを “完全シャットアウト” するルールを自分に課していました。
最初の数日は「私、ちゃんと健康意識してるな」と満足感がありました。
しかし、そのうちにこんなことが起きはじめました。
- ルールを破ると罪悪感が残る
- スマホを見ないことで“考え事のループ”に入ってしまう
- 「無理やり眠らなきゃ」と思ってかえって
結果として、眠りが浅くなり、朝の寝起きが悪くなったのです。
科学的視点:確かにブルーライトの影響はあるが…
スマホなどのブルーライトがメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑えることは、研究で明らかになっています。
ただし、それは明るさ・画面との距離・使用時間に強く依存しており、
必ずしも「寝る前のスマホ=悪」ではないという意見も増えています。
さらに、就寝前のリラックスや感情処理のために「軽い娯楽や日記アプリを使うことが効果的」とする知見もあります。
やめてからどう変わったか?
私は「完全禁止」のルールを手放し、“質”を見直す方針に切り替えました。
具体的には:
- スマホの輝度を最低に設定
- ブルーライトカット眼鏡を併用
- SNSではなく、読書アプリや睡眠誘導音楽を使う
これにより、「眠らなきゃいけない」という緊張感がやわらぎ、自然に入眠しやすくなったのです。
代替提案:光を制御して“リラックス導線”をつくる
私が今でも続けているのが、ブルーライトカット眼鏡と間接照明の活用です。
とくに照明は、部屋の色温度を“暖かいトーン”に変えるだけで眠気を促すことが複数の研究で示唆されています。



出典:Blue light has a dark side
What Color Light Helps You Sleep?
Correlated colour temperature of morning light influences alertness and body temperature
Effect of lighting illuminance and colour temperature on mental workload in an office setting
③ 毎日1万歩のノルマをやめた:数字に縛られて逆に疲れていた

健康のために「1日1万歩歩きましょう」という言葉、よく聞きますよね。
私も例に漏れず、一時期はスマホの歩数アプリを見ながら、「今日あと2,000歩足りない…」と、部屋の中を行ったり来たりしたり、夜に無理やり歩いたりしていました。
最初は “達成感” がありましたが、次第にこんな負担を感じるようになりました:
- 歩けなかった日に罪悪感を持つ
- 無理やり歩いて疲れが残る
- 数字だけが目的になり、「何のために歩いているのか」わからなくなる
続けるうちに、「数字に縛られて運動がストレス化している」ことに気づいたのです。
科学的に「1万歩」に根拠はあるのか?
実は「1日1万歩」という基準は、1960年代の万歩計の広告コピーに由来するとされ、医学的な裏付けがあって広まったわけではありません。
近年では、高齢者・中年層における健康効果は「1日6,000〜8,000歩程度」でも十分という研究も出ています。
また、ウォーキングの“質”が重要であるとも指摘されています。
やめてからどう変わったか?
私は「1万歩」にこだわるのをやめ、以下のようなスタイルに変えました:
- 昼に30分の階段登り降りを週3〜5回
- 平日5,000〜6,000歩、休日は自然に任せる
- 「今日やる/やらない」は気分と体調で決める
このシンプルな変化で、以下の効果を感じています:
代替提案:「移動」より「筋肉を使う時間」を意識する
ウォーキングよりも、下半身の大きな筋肉を使う運動(太もも・お尻)を取り入れることで、効率的な代謝アップや血流改善が期待できます。
私が今も続けているのは、「朝の階段登り降り」。
気軽にできて、習慣化しやすい点が魅力です。



出典:Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts
How many steps lead to longevity? Study identifies new daily goals
Research Shows Significant Cardiovascular Benefits at 6,000 Daily Walking Steps
How many steps do you need a day to see health benefits?
Forget 10,000 steps — study reveals the real number of minimum daily steps you should take, according to your age
④ 健康グッズの新商品チェックをやめた:「情報疲れ」で何も続かなくなった

SNSやYouTubeで「最新の健康グッズ」や「話題のサプリメント」が紹介されるたび、つい気になってしまいませんか?
私も以前は、「これを使えばもっとよくなるかも」と思い、Amazonや楽天のレビューを見ては、ポチポチと新しいグッズを試していました。
- EMSマシン
- 睡眠計測アプリ
- ストレッチ器具
- 高機能なプロテインシェイカー…
一時的にはモチベーションが上がるものの、結果的に「使わなくなる」「続かない」ということがほとんど。
それどころか、「また使わなくなった」という小さな自己否定の積み重ねが起きていました。
科学的視点:「選択疲れ」と継続率の関係
心理学では、“選択肢が多すぎると人は決断に疲れ、行動を継続しにくくなる”という「決定疲れ(Decision Fatigue)」の概念が知られています。
やめてからどう変わったか?
私は「新商品を追うのをやめる」と決めてから、以下のように切り替えました:
- 自分が続けられている定番アイテムを優先
- 「見た目や機能」ではなく「習慣として根付いたか」で評価
- 新しいものは “試す前に比較表をつくる” ことをルール化
これにより、モノに振り回されることが減り、健康習慣が “自分の軸” に戻った感覚があります。
代替提案:「“続いている”実績がある定番グッズ」に絞る
ここ数年で、本当に使い続けられている健康アイテムは3つだけです。
私の場合は、次の3つです:
- 水素水(朝の水分補給)
- 青汁(毎朝のルーティン)
- スマートウォッチ(運動・睡眠・体調の可視化サポート)
水素水や青汁は「摂る」習慣、スマートウォッチは「振り返る」習慣のきっかけになっています。
どれも毎日の行動や状態を見える化・習慣化してくれる、私にとっての “健康サポーター” です。


出典:Decision fatigue
Decision Fatigue: A Conceptual Analysis
The Psychology of Decision Fatigue: Why Many Find Comfort in Authoritarian Leadership
Overchoice
What doctors wish patients knew about decision fatigue
⑤ 「全部やろう」とする完璧主義をやめた:理想に縛られて挫折する悪循環

朝活、運動、腸活、サプリ、瞑想、早寝早起き…。
40代になってから「やったほうがいい」と言われる健康習慣がどんどん増え、「私も全部やらなきゃ」と思い込むようになっていました。
最初のうちはToDoリストをつくり、チェックを入れて達成感を感じていました。
でも、仕事が立て込んだ日や体調が優れない日に1つでもできなかっただけで、「なんでできなかったんだろう」と落ち込む日が続くようになりました。
結果的に、「できなかった自分」に疲れ、健康のために始めたはずの習慣が、逆に自己否定を生む原因になっていたのです。
科学的視点:「完璧主義」は継続の敵
心理学の研究でも、「完璧主義的傾向が強い人ほど、健康行動の継続率が下がる」ことが報告されています。
また、「習慣が途切れたときにどう反応するか」が習慣形成に最も影響するともいわれています。
やめてからどう変わったか?
私は完璧主義を手放すために、次のようにルールを緩めました:
- 「毎日やる」ではなく「週に3日できたらOK」にする
- 朝活ができなかったら「夜に深呼吸3分」でOK
- 運動できない日は「ビタミンとっておけばOK」など “最低限リカバリー”
このように、「すべてできなくてもOKな余白を用意する」ことで、習慣を続けることへのハードルが大きく下がりました。
代替提案:「完璧」より「柔軟にできる小さな習慣」へ
健康は積み重ねの総量で決まるので、途中で止まってしまうより、多少抜けても続けることのほうが圧倒的に重要です。
私が助けられたのは、“完璧にやらなくてもいい” 仕組みがあるグッズや習慣アプリの存在でした。


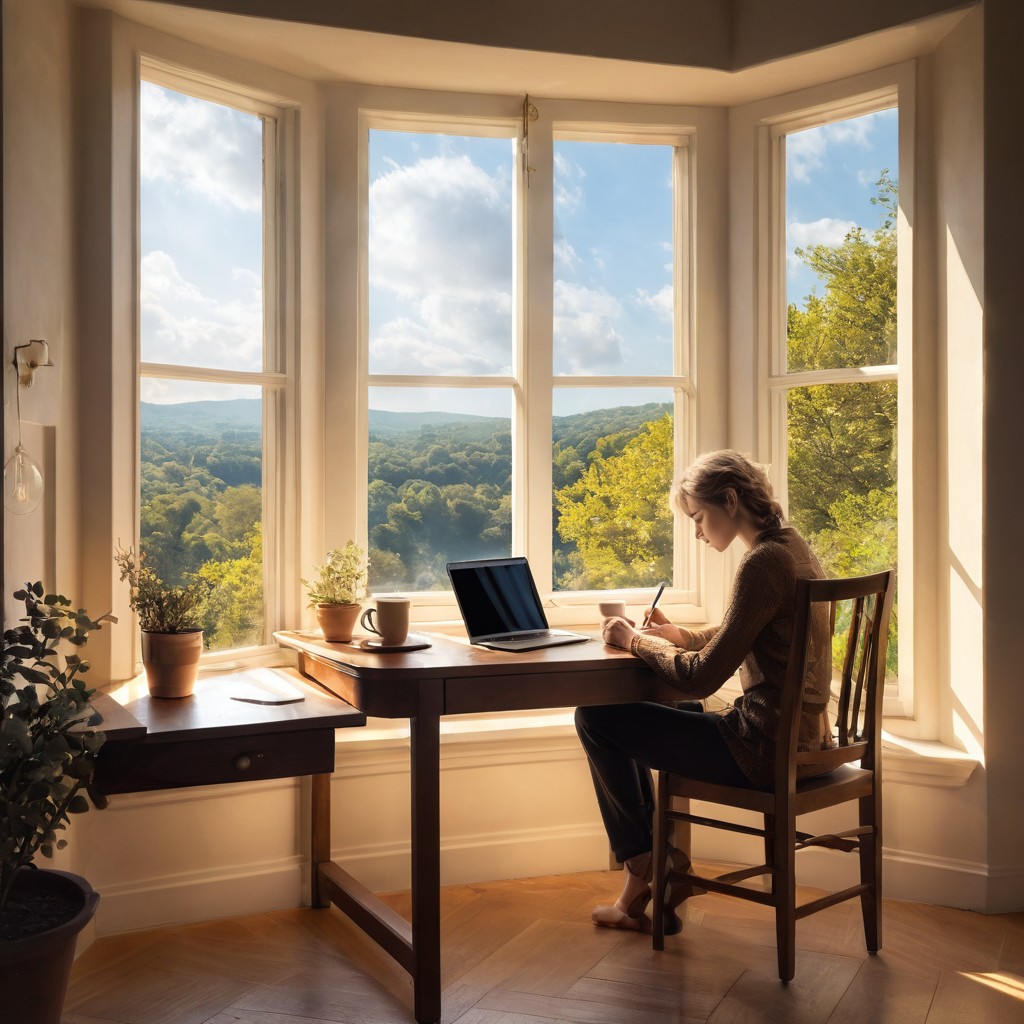
出典:Positive conceptions of perfectionism: approaches, evidence, challenges
When perfectionists adopt health behaviors: perfectionism and self-efficacy as determinants of health behavior, anxiety and depression
A Systematic Review on the Psychological Effects of Perfectionism and Accompanying Treatment
Perfectionism (psychology)
まとめ:やめたことで、健康はむしろ “整った”


今回ご紹介した「やめた健康習慣」は、どれも一度は「いい」と思って取り入れたものでした。
けれど、続ける中で「なんだか違う」「むしろ疲れているかも」と感じたのもまた事実です。
40代以降の健康習慣にとって大切なのは、「たくさんのことを完璧にこなす」ことではありません。
むしろ、“合わないことをやめて、自分にとって無理なく続けられる習慣に絞ること”のほうが、心も体もラクになります。
今回やめた習慣と、代わりに続いていること
| やめたこと | 今続けていること |
|---|---|
| ストイックな糖質制限 | 朝の青汁×腸活意識の食事 |
| 寝る前のスマホ完全禁止 | 照明&ブルーライトカットで “光環境” を整える |
| 毎日1万歩のノルマ | 朝の階段登り降り |
| 健康グッズの新商品チェック癖 | 信頼できる定番の愛用品を継続 |
| 完璧主義 | 週3できたらOKの “柔らかい習慣設計” |
こうして振り返ると、どれも「引き算の発想」がベースにあります。
情報や商品に振り回されず、“自分基準”の健康習慣を積み重ねることこそ、40代からの本質的な健康法かもしれません。
おことわり
本記事は、筆者個人の体験および調査に基づく情報提供を目的としたものであり、特定の健康法や食品・サプリメントの効果を保証するものではありません。
また、医学的診断・治療・予防を目的としたものではありませんので、ご自身の体調や疾患については必ず医師などの専門家にご相談ください。
本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

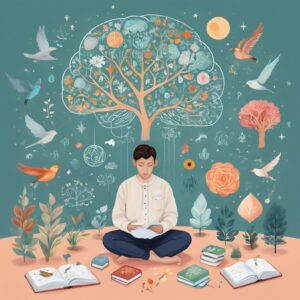









コメント